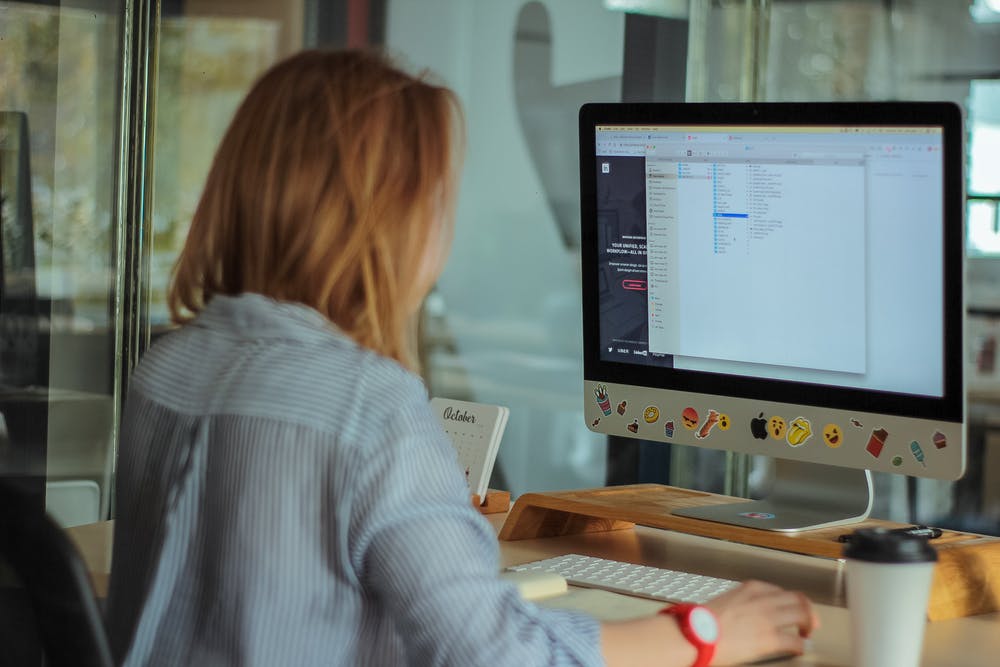一般健康診断の種類や違いを説明しましたが、それに対して産業保健師はどのようなことをしているのでしょうか。
本記事では、健診にまつわる産業保健師業務についてお伝えしていきます。
健康診断後の事後措置の流れ
まず、健康診断後の事後措置を含めた一連の流れについて、どの法令が関連するのかを確認しましょう。
1)一般健康診断の実施
対象従業員全員が期間内に受診できるよう配慮します。
結果に対して健診機関の医師の判定が入ります。
・結果票は5年間保存しなければなりません。
労働安全衛生規則
第五十一条
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票様式第五号(一)(二表面)(二裏面)(三)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
引用元: 安全衛生情報センター
・50人以上の事業場は所轄監督署へ結果報告を行います。
労働安全衛生規則
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書様式第六号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
。
引用元: 安全衛生情報センター
2)健診結果を従業員へ通知する
労働安全衛生法
第六十六条の六
事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
引用元: 安全衛生情報センター
3)健診機関の判定結果を確認
・結果判定に基づき、二次健康診断対象者になっている者を把握して受診勧奨を行うとともに、二次健診結果提出依頼を行う。
・「所見あり」の場合、必要に応じて、医師や保健師によって保健指導を行う
第六十六条の七
事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
引用元:安全衛生情報センター
4)医師により就業区分判定を行う
事業者は医師の意見(就業区分判定)をきかなければなりません。
就業区分判定
・通常勤務
・就業上の措置(就業制限)
・要休業
労働安全衛生法
第六十六条の四
事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
引用元: 安全衛生情報センター
5)従業上の措置の決定、休業指示
事業者は、医師の意見を参考に当該従業員の就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮を行います。
労働安全衛生法
第六十六条の五
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
引用元: 安全衛生情報センター
就業判定に関する参考サイト
-

-
産業保健師の業務で比重の大きい「5つの健康診断」とは?
産業保健師の業務の中で、大きな割合を占めるのが、この健康診断に関する業務です。 健康診断って5種類もあるの?何が違うの?? 本記事では、こんな疑問にお答えします。 関係法規の確認:労働安全衛生法、 ...
続きを見る
一般健診に関連した具体的な産業保健師業務
まず、産業保健師としての私の位置付けは以下のようになります。
・中小企業勤務
・正社員
・事業所ごとに保健師がひとりずつ配置されている=ひとり職場
・事務作業は基本的に事務の方々が行っている
・当事業所への産業医勤務回数は週1回(事業所により異なる)
私の会社では、6月下旬に会社で健康診断が行われます。可能な場合はそのときに健診を受診します。
受けられない場合には、自分で他の健診機関へ行って健診を受け、結果を会社へ提出します。
健診に関して産業保健師である"私"が行うこと
・7月下旬に健診結果を受け取る(用紙)
会社で受診した全員分の結果がまとまって返ってきます。
会社で受診をしてくれれば一斉に結果が出ますが、1/2~2/3程度しか受診ができないので、後は他院で受診をしてもらいます。
・結果データをシステムへ入れる
会社での受診であれば、健診機関からデータをいただき、事務方がシステムへデータを入れてくれます。
会社受診でなければ、こちらで結果内容をシステムへ手入力します。
・法令項目の受診状況を確認
会社受診であれば基本的に法令項目(受診必須の検査項目)をクリアしているはずですが、中にはなぜかスキップしたりしている場合もあることや、外部医療機関での受診の場合にも同様に項目がクリアできていない場合があるので、結果内容の確認とともに、法令項目をクリアできているかの確認も同時に行っていきます。
・健診結果の判定を確認(A~F判定)
A 問題なし
B 要注意
C 要観察
D 要受診
E 要医療
F 要治療継続
判定の詳細は特に最初に押さえる必要はありませんが、二次検査対象者や面談の優先順位を決めるにあたり、結局確認することになるので、健診結果に目を通すときにしっかりと判定も確認しておきます。
・再検査者を確認(D判定者)、再検査は8月
会社での健診を受けた場合は、再検査も会社で受診できるようになっています。
・産業医へ全健診結果を渡す
産業医より就業判定をしていただきます。
また、保健指導面談が必要か否か、必要な場合は産業医と保健師どちらが行うかを産業医に確認します。
・面談の日程調整をする
面談の必要な人の中で、早めに医療機関につなげるべき人など、優先順位をつけて面談の日程を調整します。
ここまでを7月中に終わらせます。
・面談を随時実施(集合健診の面談は8月~12月に実施)
・9月に再検査結果を受け取り、再度産業医へ確認依頼をする
面談が必要な場合には上記同様、実施者を確認し、日程調整を行います。
・基本的に、データ不良者は産業医、データ軽度不良者は保健師が面談するような区分けになります。
判断基準としては、社内規定の数値と、産業医の判断によるものになります。
・年内に終わるくらいのペースで面談を行い、健診結果のフォローアップを行っていきます。
産業医が行う面談の際、結果の数値が社内規定にかかるくらい悪い場合には、就業制限をかけます。
つまり「体調が良くないので十分に仕事ができません」ということになり、残業や出張など身体への負荷が大きいものを禁止したり制限を設けたりします。
また、受診勧奨や再検査勧奨、紹介状作成などを行っていきます。
保健師が行う面談では、食事や運動など健康支援ベースの話になります。
該当者には特定保健指導も開始していきます。
・全てExcelで管理
健診結果をこちらで受け取っていることがわかるようにする必要があります。
面談に関しては、各対象者に対していつ誰が面談を行ったのかがわかるようにしておきます。
※健診準備は行いません
健診機関との日程調整や当日の準備などは全て事務方が行ってくれるので、医療職は事後措置のみをおこないます。
健診業務のピーク時期
健診にまつわる業務は、年中行っていますが、とりわけ集団検診の時期がとても忙しくなります。
それは、結果が一気にこちらへ渡されるからです。
そうすると面談対象者も多くなり、健診結果を確認しながら面談の日程調整を行い、自分も保健指導や特定保健指導を行うなど、目が回るような忙しさになります。
ピークは健診結果が終わってから年内いっぱいというところでしょうか。
自分の時間は作ることができる
上記でお分かりのように、面談の日程調整を行うのは私なので、用事があればその日を空けたりと、自分の都合で調整をするこが可能です。
ただ、あまりのんびりすると年内に終わらないので、後で困ります。
保健指導時期について
保健指導を年内に終わらせなければならないということはありません。
あくまでも目安で、6月下旬に受けた健診を7月下旬に結果確認し、その内容に関わる面談を遅い時期に行っても、受診者自身が健診時期の状況をよく覚えていなかったりするので。
本当は、受診3ヵ月以内に保健指導を行うくらいが一番良いと思うのですが、マンパワー的に無理なので、どうにか年内を目標に計画をしている感じです。
日程調整がとても大変
日程調整はほぼメールで行います。
健診結果について保健指導を行うという理由で、健康管理室まで足を運んでいただきます。
日程調整は私が勝手にスケジュールを組みます。
ひとりあたり30分くらいの枠で面談予定を組みます。
ですが、従業員さんは皆忙しいので、スケジュールを変更することが多いです。
都度対応している状況です。
面談形式は様々
常時会社内で業務を行っている場合は問題ありませんが、出張に行っていたり、様々な理由で面談に来られないケースもありますので、その際はPC画面を通したWEB面談を行います。
それさえできない場合には、電話での面談という形になります。
最後に
いかがでしたか?
なんとなく、健診に関する業務がイメージできましたか?
これは私の会社だけの一例で、前にいた会社では全く別の方法や処理の形を取っていたので、会社によって様々です。
私のいる会社のようにアナログタイプなのか、もしくはデジタル化されているのかでも大きく異なります。
ただ、法令にもあるような流れのポイントは変わらないのでご安心ください。
ご参考まで。